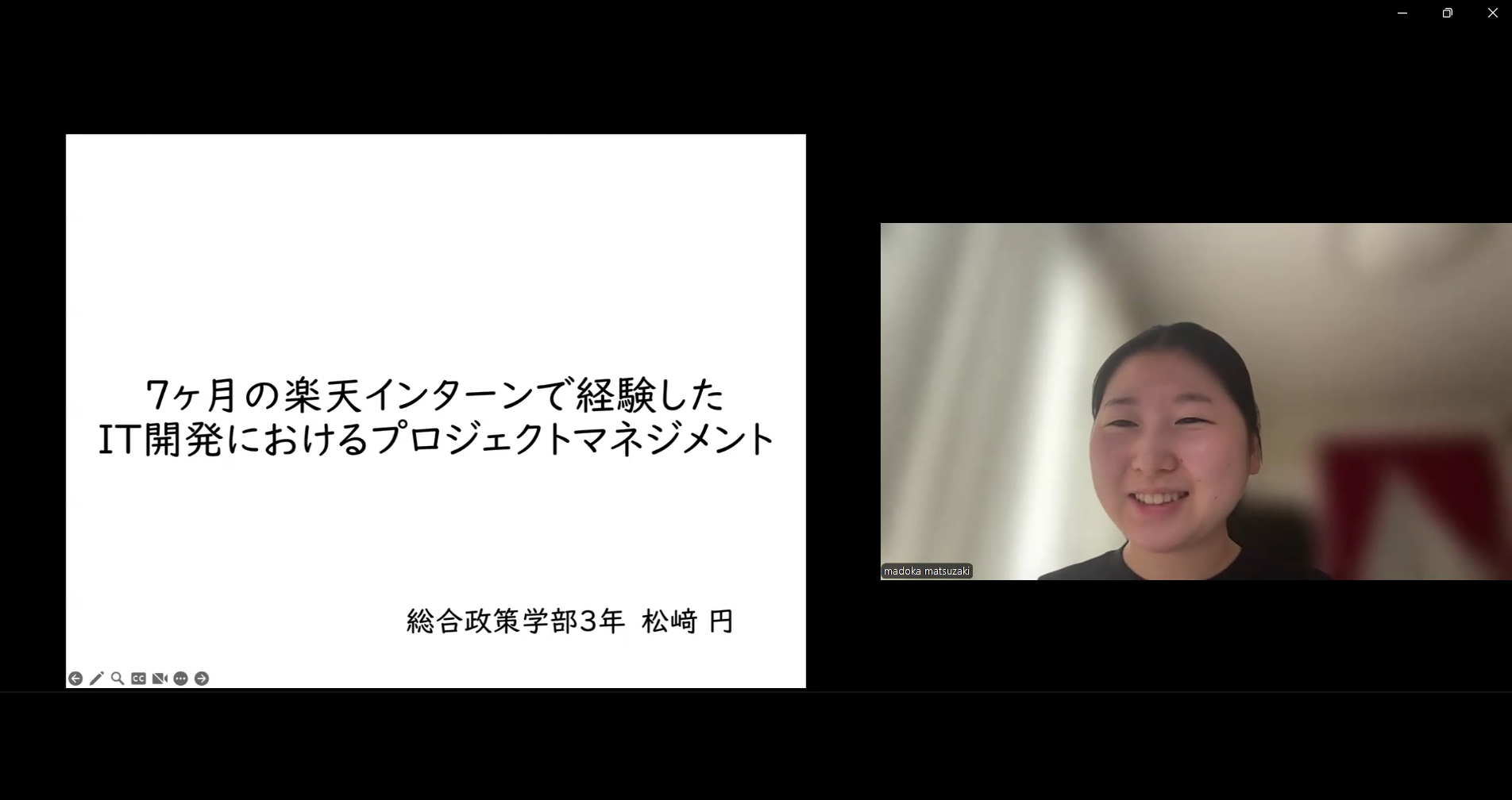多文化・国際協力学科3年 S.O.さん
多文化・国際協力学科3年 S.K.さん
JOICFPインターンシップへの応募動機
私たちがJOICFP(ジョイセフ)のインターンシップに応募したのは、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)という「自分の体と性について、自分で選び、守ることができる権利」理解をより深めたいと考えたからです。
卒業研究では女性の健康問題を扱いたいと思っていましたが、なかなかテーマが定まらず、そのヒントを得るためにもこの機会に挑戦しました。また、JOICFPの活動を知って以来、関心を持ち続けていたものの、インターンや新卒募集が見つからずにいた中、大学経由で今回の募集を知り、「今しかない」と感じて応募しました。ジェンダーや女性特有のライフステージにおける課題にも関心があり、社会の理解を深めるとともに、政策提言が行われる実際の場を学びたいという思いがありました。加えて、国際協力の現場で働く方々の姿勢に触れることで、自分たちの進路をより具体的に描きたいと考えました。

JOICFP事務所前で
現場での学びと印象的な講義
JOICFPのインターンシップでは、JICAより受託されている国際研修の来日期間(3週間)の運営補助として関わりました。
国際研修にはアジア・アフリカ・中南米の10か国から12名の行政官や医師等が参加していました。各国の研修参加者と一緒に受けさせていただいた講義や現場訪問を通じて、日本の出産・育児支援には地域の人々や多様な立場のアクターが関わっていることを知りました。海外からの研修参加者との交流では、支援が届きにくい背景に交通の不便さや文化的な考え方があることを学び、母子手帳の使い方も国によって異なることを実感しました。日本で当たり前に得られるサービスが不十分である現状に、研修参加者の人々が疑問を呈し、活動計画を短い期間で制作していく姿に、力強さを感じました。
また、特に印象に残ったのは、外部講師のお一人である「藤沢女性のクリニックもんま」門間美佳先生の講義です。日本の性教育の不十分さが、子どもや若者の自己防衛力の弱さにつながっている現状を知り、幼少期からの性教育の重要性を強く感じました。また、ユースクリニックのように、性に限らず幅広い悩みを相談できる場の必要性についても理解を深めました。
そして、各国の母子手帳の工夫や、日本の母子手帳の歴史的背景を学ぶ中で、国際協力においては一つのモデルをそのまま適用するのではなく、文化や環境に即した仕組みづくりが必要であることを実感しました。

研修参加者と一緒に訪問した子ども家庭支援センター
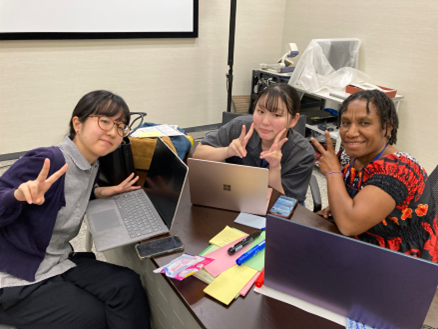
研修参加者が自国に戻った後の活動計画の作成を補佐
自身の成長とキャリアへの気づき
このインターンシップを通じて、自分たちの卒論に向けた視点の広がりと、キャリアへの気づきを得ることができました。
まず、子育てをしている人が自分らしく過ごせる社会の実現を目指したいと思うようになりました。実現のためには、行政や医療の支援だけでなく、身近な人との気軽な対話や経験・知識の共有の場が必要だと感じ、若者同士の活動や育児経験者との交流を支えるようなキャリアを目指したいと考えています。
また、語学力の不足が現地での理解やコミュニケーションに限界をもたらすことも痛感し、今後は語学学校や大学の留学プログラムを活用して語学力を高め、より深い学びにつなげたいと思っています。活動前は、興味があっても調べる習慣がなく、質問をためらうことが多かった私たちですが、今では関心分野の調べ方を身につけ、相手の状況を考慮しながら質問できるようになりました。社会人としてのマナーも学び、実践できるようになったことは大きな成果です。
今後の学びと卒論への展望
今回のインターンから得た新たな視点を、卒業論文に生かしていきたいと考えています。国際協力には多様なアクターが関わっており、その関わり方も様々であることから、自分たちはどの分野でどのように関わっていきたいのかを改めて考える機会となりました。SRHRに関する講義も大学で積極的に受講し、学びをさらに深めていきたいです。
自分の興味関心を広げること、あるいは今関心があることをより深めることの両方にうってつけの機会であり、それを達成するためには事前学習や事後の振り返り、実習中の積極的な姿勢が重要だと感じました。専門的な知識の欠如を恥じずに飛び込む勇気が、より充実した学習につながることを実感しています。
参加の意義とメッセージ
このインターンシップは、専門的な分野に関心がある人だけでなく、モザンビークやウガンダなど普段出会うことが難しい国の人々との交流や、社会人としてのマナーや常識を身につける機会としても意義があると感じています。国際協力の現場に触れることで、自分たちの視野が広がり、将来の進路や研究テーマに対する理解が深まると思います。
学びは挑戦から始まります。